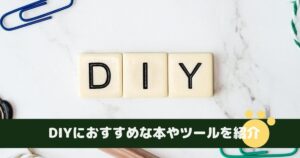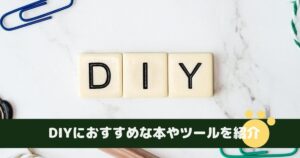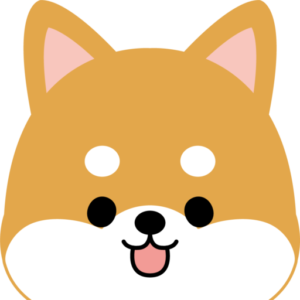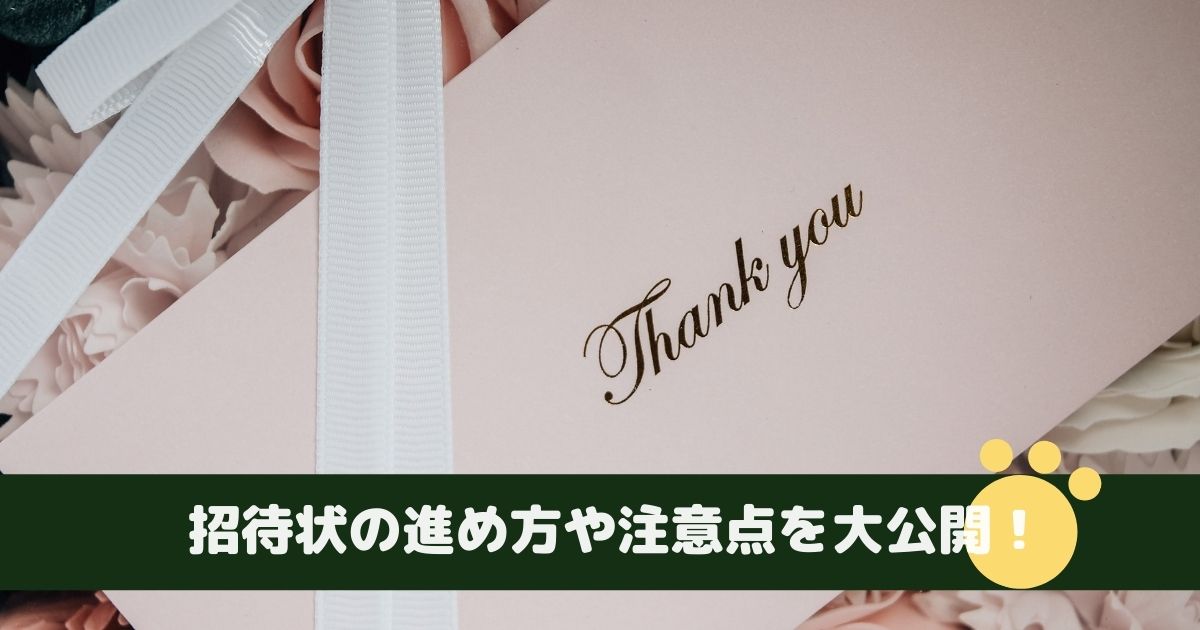結婚式の打合せの中で一番最初に行う「招待状」の打合せ。
ここから結婚式が本格的にスタートということもあり新郎新婦も身の引き締まる想いかと思いますが、招待状はゲストに対する正式な案内となるため重要かつ気を遣う部分でもあります。
式場を契約してから打合せ開始までの日数は人によって様々ですが、招待状の進め方や手作りの注意点など分かりやすくお伝えしたいと思います。
- これから打合せがスタートする方
- 招待状の手作りを検討している方
- 早めに色々準備しておきたい方
結婚式の招待状とは?

ここでいう招待状とは紙ベースの案内状を指しますが、一般的に結婚式での招待状とは、結婚式に関する情報(日時・場所・時間)を案内するもので、ゲストの出欠状況を確認するという役割があります。
招待状と言っても、これだけのものが封筒の中に同封されています。
- 本状
- 返信はがき
- 式場までの地図
- 付箋
この4点は必ず同封されていて、人によってはメッセージカードやタクシーチケット、芳名帳代わりのゲストカードが含まれる場合もあります。
本状
招待状一式の中でも一番メインとなる本状は、結婚式への参加をお願いする挨拶文や[いつ・どこで]結婚式を行うかという大切な情報が記載されています。
昔からの慣習で挙式案内は後述の付箋に記載して同封されることが多いですが、近年は本状に記載することも主流になりつつあります。
返信はがき
返信はがきはゲストの出欠席を取るためのもので、後日投函してもらう必要があるので慶事用の切手(63円)を事前に貼って同封します。
前面は新郎新婦への宛名が印字され、裏面は出欠席やゲストの氏名・住所の記入欄、アレルギー項目やメッセージ欄が設けられています。
式場までの地図
遠方や土地勘のないゲストにとって重要な会場までのアクセス情報も同封します。
車・電車・バスなど様々な交通機関の情報も必要ですし、写真のようにQRコードも載せて素早くWEBにアクセスできるように配慮しておくと親切ですね。
付箋
付箋の種類は下記のように2タイプあり、集合時間を伝える付箋はどれか1つ該当するものが必ず同封され、役割を伝える付箋は特定のゲストに同封します。
- 受付
- 親族紹介
- 挙式
- 祝辞
- 乾杯
- 友人スピーチ
- 余興
招待状発送の段階で役割をお願いするのはマナー違反となるので必ず事前に依頼をしたり、式後もお礼をすることが一般的です。

結婚式の招待状打合せ前にやっておきたいこと

式場で招待状の打合せの際にどんなことを決めるのかというと下記の3点がメインとなります。
- 招待状のデザイン
- 文面
- はがき、封筒に印字する送り先や住所
いずれも既存のデザインや例文から選択するのでそんなに難しいことではないのですが、招待状が新郎新婦の元に納品され発送をする段階で、封筒に宛名を記入するので下記の情報を事前に調べておく必要があります。
- ゲストの名前(漢字のフルネーム)
- ゲストの住所
上記に加え、招待状が何部必要なのかも発注のタイミングで必要となるため、ゲストのリストアップも打合せ開始前に進めておくとスムーズです。
結婚式の招待状発送までの流れ
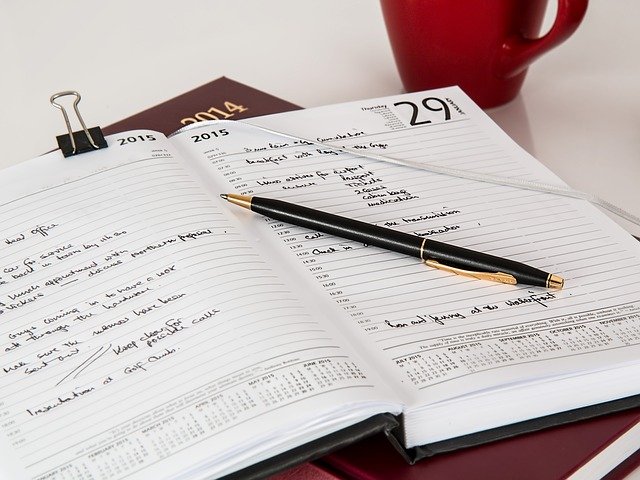
打合せ~発送までの流れは下記のとおりで、早ければ打合せから1~2週間ほどでお二人の元へ納品は可能です。
- ゲストのリストアップ、名前、住所を調べておく
- デザイン、文面、枚数を決める
- 校正確認・発注
- 納品
- 発送準備
- 発送
ゲストのリストアップ、名前、住所を調べておく
ゲストのリストアップの際は招待漏れを防ぐためにも来る・来ないは別として、招待しようと思っている方全員書き出しましょう。
その後招待状発送時に必要な漢字・住所の情報も調べ、合わせて肩書きも記載しておくと席次表作成時に役立ちます。
リストアップ表はエクセルやスプレッドシートで管理しておくと便利です。
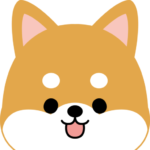 わさび
わさびニックネームで呼んでいると意外に名前の漢字を知らなかったりするから気をつけよう!
デザイン、文面、枚数を決める
式場で選ぶと紙の質感なども分かりますが、デザインを選ぶ際は季節感に注意して選んでください。
例えば8月挙式だとすると4月に招待状打合せをしますが、打合せ時が桜が咲いている時だったからそのデザインにしようと思っても、発送する時はすでに季節は変わってしまっていることになります。
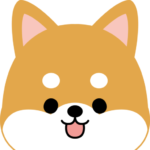
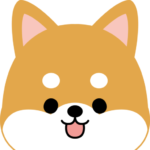
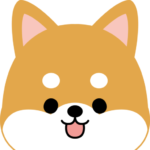
季節感のあるデザインなら発送する時期の季節に合ったものにしよう!
校正確認・発注
挙式日・名前・日時・選んだ文面等が記入されている印刷前の最終確認が必要になります。
要は間違いがないかどうかをお二人に確認していただくのですが、この確認が遅れてしまうと納品に影響が出てしまうので必要枚数も合わせて早めに確認しておきましょう。
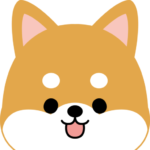
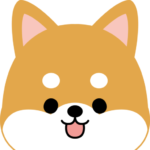
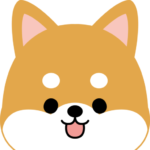
招待状発送枚数は人数分ではなく世帯分だよ!
納品
校正確認・発注が済んだら約1~2週間ほどで納品となりますが、納品前に下記の発送準備で進められるところ(返信はがき用切手の購入など)があるとスムーズです。
発送準備
発送準備として必要なことがこちらです。
- 返信はがき用の慶事切手の購入 ※63円(2022年2月現在)
- 封筒用の慶事切手の購入 ※84円~ 重さによって変動あり(2022年2月現在)
- 封筒の宛名書き
返信はがき用の慶事切手は封筒に入れるものなので必ず事前に購入する必要があります。
返信はがきや封筒の切手を新郎新婦オリジナルの切手として使用できるサービスもあるので、詳しくはこちらの記事もご参考ください。


封筒用切手は事前購入でもいいのですが、郵送分はまとめて郵便局に出すと貼ってくれるのでそちらを推奨します。
また宛名書きは筆ペンで自分の字で書くことが必須ですが、書き損じも考えられるので封筒は少し余分に頼んでおくと安心です。
発送
宛名書き等が終わったらいよいよ発送となりますが、発送方法は郵送もしくは手渡しとなります。
発送は結婚式の約3か月前が一般的ですが、大安・友引など縁起のいい日に手渡しや消印日として郵送ができると良いですね。
結婚式の招待状を手作りをする場合の注意点


招待状といっても中身は色々なものが同封されますが、一から作成しないといけないものも多いのでこんなことに注意して作成しましょう。
- 通常よりも早めに準備する
- 紙の質感
- 購入物のサイズ
- 式場情報
- 費用
通常よりも早めに準備する
全てを手作りの場合、早めに準備をスタートしましょう。
仕事や家事と並行しながら手作りに割ける時間はどれくらいあるのか、PCやコピー機など環境は整っているかを考えながらスタート時期を見極めていきましょう。
デザインや文章もテンプレートはありますが、いざ作っていくとオリジナル性が出てくるのでそれも踏まえて早めに準備していきましょう。
新郎新婦のロゴを入れるだけでもオリジナル性はでますし、


招待状などのペーパーアイテムの手作りはCanvaという無料ツールがおすすめです。


紙の質感
こちらは好みの問題ですが、あまりにもペラペラだったりすると安っぽい印象を与えてしまいます。
招待状は厚みがあり高級感を感じられる質感が多いので、サンプルを取り寄せたりして事前に確認しましょう。
購入物のサイズ
合わせてサイズも重要になります。
一般的なサイズであれば問題ないのですが、変形サイズだと家庭用のコピー機だと対応できない場合もあります。
式場情報
地図や住所など、ゲストはこれを見てお越しいただきます。
こちらを間違えてしまうとお客様にも式場にも迷惑をかけてしまうので、必ず式場側も含めて確認しておきましょう。
費用
手作りはそもそも安くなったのかという懸念や労力や負担を伴うことが往々にしてあり、一番のメリットは費用を抑えることだと思いますが、招待状に関しては式場発注でも1部400円くらいから発注できます。
手作りがその半額だとしても印刷が必要なものも多いので、費用と労力のバランスの見極めが重要ですし、全て手作りではなく半分外注というのも一つの手だと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は招待状の進め方などについて紹介しました。
近年は手作りという選択も増えましたが、招待状に限っては用意するアイテムが細分化されていることや印刷の手間も考えると手作り難易度は高めと言えます。
結婚式の最初の打合せかつ重要な内容でもあるので、式場手配が最も負担なく進められるのではないでしょうか。
本日のまとめはこちらです。
- 招待状を送る前の準備を万全にしておく
- 手作りの場合は早めに動く!
- 印刷だけ外注というハイブリッドなスタイルもおすすめ!
それでは素敵な結婚式を♪